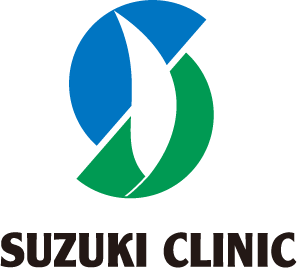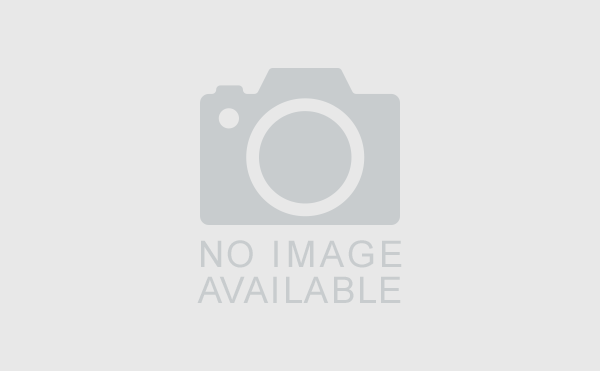小児科
成長や発達の途中にある子どもは、同じ病気でも大人とは異なる症状が現れ、治療方法も成長段階に応じて変わることがあります。
当院では、内科診療を中心に幅広い年齢層の患者さんを診療しています。小児科専門ではありませんが、小さなお子さまの診療にも丁寧に対応し、必要に応じて専門医療機関と連携しながら最適な医療を提供することを心がけています。
院長は8人の孫を持つ祖父として、副院長は男の子と双子の女の子の父として、同じく子育て中の親御さんに寄り添った診療を行っております。
お子さまの健康についてお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
なお、当院では予約優先制を採用しております。直接ご来院された場合でも診察させていただきますが、待ち時間が多く発生する場合があります。発熱のある方は、発熱外来の予約をお取りください。
小児科の受診目安
子どもは体調を崩しやすく、特に小さなうちは些細な症状でも心配になりますよね。
小児科の受診を検討した方が良い症状の目安や、受診の際にあらかじめ確認しておきたい注意点をご紹介します。
小児科を受診した方が良い症状
生後3か月以上で、熱があっても食事や水分が十分に摂れて元気があれば、すぐに受診せず様子見をしても構いません。
一般的に、以下のような症状がありましたら、小児科の診療時間内での受診を検討されると良いでしょう。
- 発熱が5日以上続く
- 機嫌が悪い、おもちゃなど周りに興味を示さない
- 水分が摂れなくて、おしっこが出ない
- 昼夜問わず咳が出る
- 嘔吐や下痢が続く
- 発疹が急に出て、広がっている
すぐに受診した方が良い症状
ただし、以下の場合には救急病院を含め、すぐに受診するようにしましょう。
- 生後3か月未満の赤ちゃんの発熱
- 高熱が続いている上、嘔吐するようになった
- ひきつけ(けいれん)を起こした
- ぐったりしている、反応が鈍い
- ゼイゼイとした咳が出る、肩で息をするような呼吸をしている、息苦しさがある
上手な受診の仕方
小児科を受診されるときは、次のような点に注意すると、スムーズに受診できることでしょう。
症状の経過をメモする
どんな症状か、いつから症状が出たか、発熱の経過、食事・水分摂取の状況、今までにかかったことのある大きな病気、薬のアレルギー、家族に同じ症状が出ているか、といったメモは、診断の重要な情報源となります。気になる発疹・症状は、写真や動画を撮っておくと伝えやすいです。

受診の際は、お子さんの状態を説明できる人が付き添う
乳幼児の場合、自分の症状をうまく伝えられないことも多いので、症状の経過や状態を説明できる方が受診に付き添うようにしましょう。もし、別の方が付き添う場合には、説明できる方が状況を書いたメモを渡すなどして、できるだけ多くの情報を医師に伝えるようにしてください。
持参すると良いもの
- 母子手帳、保険証、医療証、お薬手帳
- 便の状態がおかしいときは便をお持ちください。おむつのままでも構いません。
- 待ち時間が長くなるときのために、お気に入りのおもちゃなどを持参されると良いでしょう。
診察前には、食べ物・飲み物を与えない
口の中がよく見えなくなってしまうので、診察前の飲食は避けてください。
待合室でトイレに行きたくなったら、スタッフに声をかける
発熱、嘔吐、腹痛があるとき、尿検査をすることがあります。そのため、待っている間におしっこがしたくなったら、スタッフまでお声がけください。
小児科で扱う主な疾患
子どもに多い主な病気には、次のようなものがあります。
なお、近年、子どもの病気や不調に漢方薬が効果を発揮するケースが増えています。
当院でも必要に応じて漢方薬を処方しております。
感染症
現在、一部の感染症に対して、発症および重症化予防として予防接種が行われています。法律で接種が勧められている定期接種では、接種費用の公費負担があります。
【1年中感染しやすい病気】
風邪(かぜ症候群)
風邪は正式には「かぜ症候群」と呼ばれ、主にウイルス感染(ライノウイルス、コロナウイルス、RSウイルス、アデノウイルスなど)が原因で起こる上気道(鼻からのど)の感染症の総称です。一般的にくしゃみ、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、咳、発熱、頭痛など様々な症状が現れます。通常、軽症で経過するため、数日から1週間程度で自然治癒しますが、高熱が続く、ぐったりするなどの場合には、すみやかに医療機関を受診しましょう。
風邪のウイルスは200種類以上あり、さらに同じウイルスで複数の型があるため、一度治っても再び感染します。
百日咳
百日咳は、百日咳菌による感染症で、発作的な咳が数週間から数か月続く特徴があります。特に乳幼児は重症化しやすく、呼吸困難を引き起こすことがあるため、三種混合(DPT)や四種混合(DPT-IPV)ワクチンが推奨されています。しかし、近年ワクチン効果が低下する学童期や思春期、大人の発症が増加しています。症状は3段階に分かれ、最も感染力の強い「カタル期」では風邪に似た症状(微熱・鼻水・乾いた咳)が1~2週間続きます。その後、「痙咳期(けいがいき)」では激しい咳と笛のような呼吸音が2~4週間続き、最後に「回復期」で徐々に咳が落ち着きます。抗生物質により治療しますが、再感染の可能性があるため注意が必要です。感染力は初期に高くなるため、風邪が長引く場合は早めの受診をおすすめします。
【春に感染しやすい病気】
溶連菌感染症
溶連菌感染症とは、A群溶血性連鎖球菌(溶連菌)という細菌が主にのどに感染することにより、のどの痛み、発熱(38℃~39℃)が出る咽頭炎(いんとうえん)です。風邪のように鼻水や咳が出ないのが特徴です。ほかに、小さくて赤い発疹、舌に苺のようなブツブツ(イチゴ舌)が現れることもあります。現在は、のどの奥から細菌をぬぐって5~10分程度で診断できる検査法が確立されています。治療には抗生物質を使用しますが、症状が軽減しても最後まで飲み切って溶連菌を退治することが大切です。溶連菌感染症は適切な治療を受けないと、心臓に障害を起こすリウマチ熱や、急性糸球体腎炎などの重篤な合併症を引き起こすことがあります。
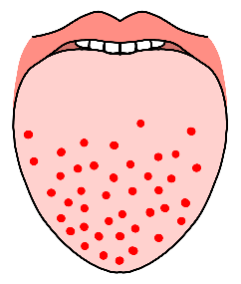
おたふく風邪(流行性耳下腺炎)
おたふく風邪はムンプスウイルスによる感染症で、耳の下(耳下腺)や顎の下(顎下腺)が腫れ、痛みを伴います。一般的に片側から始まり、数日以内に両側が腫れますが、片側だけのケースや、約3割が症状の出ない不顕性感染となることもあります。腫れは通常1週間程度で治まり、特効薬はなく、解熱鎮痛薬や冷却による対症療法が中心です。多くは軽症ですが、髄膜炎、脳炎、ムンプス難聴、精巣炎・卵巣炎などの合併症が起こることがあります。特に15歳以上の感染では精巣炎・卵巣炎の発症リスクが約30%高まります。日本小児科学会では、発症および重症化予防として、2回のワクチン接種(任意接種)を推奨しています。
はしか
はしかは麻疹ウイルスによる感染症です。感染力が非常に強く、空気感染もするため、免疫のない人が感染すると、ほぼ100%発症するとされます。10~12日程度の潜伏期間を経て、風邪のような症状から始まり、3日くらい経過すると40℃近い高熱、咳、鼻水、発疹といった特徴的な症状が1週間程度続きます。また、中耳炎や肺炎、脳炎を合併することがあります。特効薬はないので、症状を和らげる対症療法を行います。予防として、MRワクチン(麻しん・風しん混合ワクチン)が定期接種化(2回)されています。
水ぼうそう(水痘)
水ぼうそうは、水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)による感染症で、高熱と頭皮や身体に小さな赤い水ぶくれのような発疹が現れます。発疹にはかゆみを伴いますが、1週間程度でかさぶたとなって、自然に治ります。通常軽症で済みますが、乳幼児では重症化することもあるため、注意が必要です。現在、1歳から3歳までに2回の水痘ワクチンが定期接種化されています。
風疹
風しんは風しんウイルスによる感染症で、発熱、発疹、リンパ節の腫れが現れます。同じような症状がみられる、はしかと比べて軽い症状なので、別名「3日はしか」とも呼ばれます。一方で大人が感染すると重症化することや、妊娠初期の女性が感染すると、目、心臓、耳に障害を持った先天性風しん症候群の子どもが生まれることがあるので、注意が必要です。特効薬はないので、対症療法が中心となります。通常軽症で経過しますが、関節炎や倦怠感、高熱などが現れることがあります。予防にはMRワクチンが有効で、2回の定期接種が推奨されています。
【夏~秋に感染しやすい病気】
代表的な夏風邪として、手足口病、ヘルパンギーナ、プール熱(咽頭結膜熱)があります。
手足口病
手足口病は三大夏風邪のひとつで、乳幼児に多い感染症です。コクサッキーウイルスやエンテロウイルスの感染が原因となり、最初に発熱やのどの痛みが現れ、1~2日後に手のひら、足の裏、口の中に水ぶくれのような発疹ができます。まれにお尻や膝にも広がることがあります。ウイルスは、飛沫感染や接触感染によって感染します。特効薬はなく、治療は対症療法が中心で、痛みが強い場合は解熱鎮痛薬を使用します。脱水症状にならないよう、水分補給を十分に行うことが重要です。ほとんどの場合、1週間程度で自然に回復しますが、まれに髄膜炎などの合併症を引き起こすことがあるため、症状が重い場合は早めに受診しましょう。
ヘルパンギーナ
ヘルパンギーナは三大夏風邪のひとつで、乳幼児に多い感染症です。コクサッキーウイルスなどのエンテロウイルスが原因となり、突然の高熱(39~40℃)が1~3日程度続きます。また、のどの奥に小さな水ぶくれや潰瘍ができ、強い痛みを伴うため、食事や水分を摂ることが難しくなる場合があります。感染経路は飛沫感染や接触感染となります。特効薬はなく、治療は解熱剤の使用や水分補給などの対症療法が中心です。通常は1週間程度で自然に回復しますが、まれに脱水症状や熱性けいれんを引き起こすことがあるため、高熱が続いたり、水分が摂れなかったりする場合には早めに受診しましょう。
プール熱(咽頭結膜熱)
プール熱は正式には咽頭結膜熱と呼ばれる感染症です。三大夏風邪のひとつで、乳幼児や学童に多くみられます。アデノウイルス感染が原因となり、主な症状は発熱(38~40℃)、のどの痛み、結膜炎(目の充血や目やに)で、発熱は3~7日続くことがあります。塩素濃度の不十分なプールを介して感染しやすく、飛沫感染や接触感染でも広がります。特効薬はなく、治療は解熱剤の使用や水分補給などの対症療法が中心です。通常は1週間程度で自然に回復しますが、高熱が続いたり水分が摂れなかったりする場合には早めに受診しましょう。
RSウイルス
RSウイルス感染症は、生後1歳までの乳幼児に多い呼吸器の感染症で、RSウイルスが原因です。近年では夏頃から流行が始まり、飛沫感染や接触感染で広がります。初感染時は重症化しやすく、生後6か月未満(特に1~2か月)では約2~3割が細気管支炎や肺炎を合併し、呼吸困難となることがあります。症状は発熱、鼻水、せきなど風邪に似ていますが、重症例では入院し酸素吸入などが必要になります。特効薬はなく、治療は対症療法が中心です。早産児や基礎疾患のある乳児には、抗体製剤(シナジス)による予防接種が推奨されています。感染予防には、手洗いやマスクの着用が有効です。
※当院ではシナジス注射は対応しておりません。
【冬に感染しやすい病気】
インフルエンザ
インフルエンザは、A型またはB型インフルエンザウイルスによる感染症で、突然の高熱(38℃以上)、せき、のどの痛み、全身のだるさや筋肉痛が主な症状です。子どもではまれに急性脳症を引き起こすことがあり、注意が必要です。飛沫感染や接触感染で広がりやすく、学校や保育園での集団感染も見られます。治療には抗インフルエンザ薬があり、発症から48時間以内の服用が効果的です。併せて安静と水分補給を心がけましょう。インフルエンザウイルスは毎年変異するため、その年の流行を予測したワクチンの接種が推奨されています。予防策として、手洗いやマスクの着用も有効です。
感染性胃腸炎
感染性胃腸炎はウイルスや細菌による胃腸の炎症で、特に乳幼児に多くみられます。ウイルス性(ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルスなど)は冬に流行し、細菌性(サルモネラ菌、カンピロバクター菌など)は夏に食中毒として発生しやすい特徴があります。症状は突然の嘔吐、下痢、腹痛、発熱で、ロタウイルス感染では白色(クリーム色)の便が見られることもあります。治療は対症療法が中心となり、こまめな水分補給と安静が重要です。ロタウイルスによる重症化を防ぐため、生後6週から24週または36週までのワクチン接種が推奨されています。感染予防には手洗いや食事の衛生管理、嘔吐物や便の適切な処理が大切です。
クループ症候群
クループ症候群は、主に1~2歳の子どもに多いウイルス感染症で、喉の奥(声帯や気管)が炎症を起こし、呼吸が苦しくなる病気です。原因の大半はパラインフルエンザウイルスで、RSウイルスやインフルエンザウイルスも関与します。特徴的な症状は、ケンケンと犬の鳴き声のような咳、嗄声(声がかすれる)、呼吸時の喘鳴(ゼイゼイ・ヒューヒュー)などで、夜間に悪化しやすいのが特徴です。重症になると、陥没呼吸(胸がペコペコとへこむ呼吸)を伴い、呼吸困難になることがあります。軽症では加湿や安静で改善しますが、重症の場合はステロイド吸入、入院治療が必要です。予防にはRSウイルス・インフルエンザの予防接種、手洗い、うがいが有効です。
マイコプラズマ肺炎
マイコプラズマ肺炎は、マイコプラズマ・ニューモニエという細菌による肺炎で、主に6歳~12歳までの小学生の子どもに多くみられます。潜伏期間は2~3週間と長く、飛沫感染や接触感染で広がり、2024年は全国的な流行がみられました。乾いた咳、発熱、倦怠感などで、初期は軽い風邪のような症状ですが、徐々に咳が強くなり、数週間続くことがあります。診断には血液検査や胸部レントゲンを用いることが一般的です。治療にはマクロライド系などの抗菌薬を使用し、同時に安静と水分補給も重要です。特効薬や予防するワクチンは現在ありませんが、日常的な手洗いやうがい、アルコール消毒で感染を防ぐことが大切です。咳が長引く場合は早めに受診しましょう。
中耳炎
中耳炎は、鼓膜の奥にある中耳に炎症が起こる病気で、特に0~2歳の乳幼児に多いです。風邪や鼻炎をきっかけに細菌・ウイルスが中耳に感染することで発症します。主な症状は、耳の痛み、発熱、耳だれ、聞こえにくさなどですが、乳児では機嫌が悪くなったり、耳を触る仕草が増えたりすることもあります。軽症では経過観察し、細菌感染が疑われる場合は抗菌薬、痛みが強い場合は鎮痛剤を使用します。発症予防のひとつに肺炎球菌ワクチンが有効で、鼻水をこまめにかむことも大切です。放置すると慢性化し、難聴や言語・学習への影響を及ぼす可能性があるため、症状が続く場合は早めに受診しましょう。
皮膚疾患
乳児湿疹
乳児湿疹は、生後2週間頃から1歳頃までの赤ちゃんにできる湿疹の総称で、赤み、かさつき、ブツブツ、水ぶくれなどが顔や頭皮、体に現れます。乳児湿疹にはあせも、赤いポツポツができる新生児ニキビ、頭皮・眉・おでこなど皮脂分泌の多い部位に黄色いかさぶたのようなものができる脂漏性湿疹、アトピー性皮膚炎と確定診断されていない湿疹など、すべての皮膚トラブルが含まれます。原因は皮脂の分泌過多や乾燥、汗、刺激物による肌バリア機能の未熟さなどがあります。治療では、症状に応じて保湿剤やステロイド外用薬を使用し、悪化を防ぎます。一方、日常的にこまめな保湿とやさしい洗浄による正しいスキンケアを続けていけば、次第に皮膚バリアが備わり、1歳頃には湿疹が落ち着いてくることも多いです。
水いぼ
水いぼは伝染性軟属腫ウイルスによる皮膚の感染症で、10歳未満の子どもに多い病気です。光沢のある白色や肌色の小さないぼ(丘疹)が体、腕、足にできて、かゆみを伴います。肌の接触、タオルの共有などで感染が広がりますが、プールの水ではうつりません。自然治癒も可能ですが、半年から5年と長期間かかり、その間に水いぼが増えたり他人にうつしたりすることがあるので、一般的には専用のピンセットでつまみ取ります。ほかにも液体窒素、外用薬、電気で焼くなどの治療があります。かき壊すととびひになったり、アトピー性皮膚炎が悪化したりすることがあるため、水いぼができたら早めに医療機関に相談した方が良いでしょう。
伝染性膿化疹(とびひ)
とびひは、主に黄色ブドウ球菌や溶血性レンサ球菌など細菌による皮膚の感染症です。すり傷や虫刺され、湿疹をかき壊した部分から細菌が入ることで発症します。症状は水ぶくれとかさぶたの2つに分かれます。水ぶくれは強いかゆみを伴い、かいた手で身体の他の部位を触ると、身体のあちこちに次々と広がります。他人へうつすことがあるので注意が必要です。一方、かさぶたでは炎症が強く、リンパ節の腫れ、発熱、のどの痛みを伴うことがあります。一般的には、抗菌薬(塗り薬・飲み薬)による殺菌、かゆみが強い場合には抗ヒスタミン薬や抗アレルギー薬を使用します。予防には日常的な手洗い、爪を短く切る、虫刺されや湿疹をかき壊さないよう注意しましょう。症状が広がる場合には早めに受診しましょう。
あせも
あせもとは、正式には汗疹(かんしん)と呼ばれる湿疹で、夏など高温多湿の環境下で発症しやすいです。原因は汗の通り道が詰まり、皮膚の中に汗がたまることなので、汗腺が未発達で汗をかきやすい乳幼児は特に発症しやすい傾向にあります。小さな赤いブツブツ(紅色汗疹)や透明な水ぶくれ(水晶様汗疹)が首、背中、額、肘や膝の内側などに現れ、かゆみを伴います。通気性の良い服を着て、汗をこまめに拭くなど、汗をかいたままにせず皮膚を清潔に保つことが治療の基本です。かゆみが強い場合は保湿剤やステロイド外用薬を併用します。
おむつかぶれ
おむつかぶれとは接触皮膚炎のひとつで、陰部やおしり、おむつが当たる太もも、下腹部の皮膚が赤く炎症して、ただれ、ブツブツができることもあります。原因は一つではなく、尿や便による刺激、摩擦、湿気による皮膚のふやけ、細菌やカビ(カンジダ菌)の増殖などに複数の要因が発症に関与していると考えられています。保湿剤と軟膏で治療します。併せて、おむつ交換の頻度を増やし、皮膚をこすらない、ぬるま湯で優しく洗う、しっかり乾燥させるようにしましょう。適切なスキンケアと清潔な環境を保つことが予防につながります。
便秘
便秘とは長期間便が出ない、または出にくい状態のことを指し、子どもにとって珍しい病気ではありません。週3回以下、または5日以上排便がない場合を便秘の目安としていますが、出すときに痛がる、1日に何回か出ても小さいコロコロ便や柔らかい便が少しずつといった場合も便秘です。特に幼児期の便秘症は放置しておくと、悪循環となり、ますます悪化しやすくなります。主な原因は水分・食物繊維不足、運動不足、排便習慣の乱れ、ストレスなどによる腸の働きの低下で、腸や肛門の病気の場合もあります。治療は食事や生活習慣の見直しであり、必要に応じて浣腸や緩下剤を使用します。予防には規則正しい生活習慣と、トイレを我慢せず、規則正しく排便することが大切です。便秘が続く場合や排便時に痛みがある場合は、早めに受診しましょう。
アレルギー
アトピー性皮膚炎
アトピー性皮膚炎は、かゆみのある湿疹を慢性的に繰り返す皮膚の病気で、乳幼児期や幼児期に発症することが多いです。赤み、かゆみ、乾燥、湿疹などの症状が顔や首、肘や膝の裏などに現れる特徴があります。原因は、皮膚のバリア機能の低下やアレルギー体質に加え、ダニやホコリ、汗、乾燥、ストレスなどの環境要因も重なって発症すると考えられています。治療の基本は保湿剤によるスキンケアと、炎症を抑えるステロイド外用薬や免疫抑制外用薬の使用となり、かゆみが強い場合は抗アレルギー薬を併用することもあります。予防として、肌や肌に触れるものは清潔に保ち、保湿を徹底し、汗や刺激物を避けることが大切です。症状が悪化する前に早めのケアを行い、必要に応じて受診しましょう。
食物アレルギー
食物アレルギーは、特定の食べ物に対する免疫の過剰反応により症状を引き起こす病気です。原因食品には卵、乳、小麦、大豆、ナッツ類、魚介類などがあり、摂取後数分~数時間以内にじんましん、かゆみ、腹痛、下痢、嘔吐、咳、喘鳴(ゼイゼイ・ヒューヒューする呼吸)などの症状が現れます。重症例では症状が強く出るアナフィラキシーを引き起こし、血圧低下や意識障害を伴うこともあるため注意が必要です。治療は原因食品の適切な除去と、抗アレルギー薬の使用が基本で、アナフィラキシーにはアドレナリン自己注射(エピペン)を使用します。予防には、医師の指導のもと適切な離乳食を進めることや、乳幼児期の湿疹治療とスキンケアが推奨されています。症状が疑われたら早めに受診しましょう。

アレルギー性鼻炎(花粉症)
アレルギー性鼻炎は、花粉やハウスダストなどのアレルゲン(抗原)に免疫が過剰に反応し、くしゃみや鼻水、鼻づまりを引き起こします。季節性(花粉症)と通年性(ダニやハウスダストが原因)の2種類があります。いずれも症状は、連続するくしゃみ、大量の透明な鼻水、鼻づまり、目のかゆみなどで、重症例では集中力や睡眠に影響を及ぼすことがあります。治療は抗ヒスタミン薬、点鼻ステロイド薬、舌下免疫療法などがあり、症状や年齢に応じて選択します。予防にはマスクの着用、こまめな掃除、花粉の多い時間帯や場所への外出を控えることが有効です。早めの対策と適切な治療で症状を軽減し、日常生活への影響を減らしましょう。
出席停止が必要となる感染症
学校保健安全法では、学校で予防すべき感染症について、出席停止の期間が定められています。
定められた感染症(学校感染症)は第一種~三種に分かれています。
※出席停止による欠席は、欠席扱いにはなりません。
| 分類 | 病名 | 出席停止の期間 | |
|---|---|---|---|
| 第一種感染症 | 一類 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 | 治癒するまで |
| 二類 | 急性灰白髄炎(ポリオ)、重症急性呼吸器症候群(SARS)、ジフテリア、鳥インフルエンザ(H5N1) | ||
| 第二種感染症 | インフルエンザ ※特定鳥インフルエンザ、新型インフルエンザなどの感染症を除く | 発症日を0日目として5日が経過し、かつ解熱後2日(幼児では3日)が経過するまで | |
| 百日咳 | 特有の咳がなくなるまで、または5日間の抗生物質治療が終了するまで | ||
| 麻しん(はしか) | 解熱後3日を経過するまで | ||
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺・顎下腺・舌下腺の膨張が現れてから5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | ||
| 風しん | 発疹がなくなるまで | ||
| 水痘(みずぼうそう) | すべての発疹がかさぶたになるまで | ||
| 咽頭結膜熱(プール熱) | 主症状がなくなった後、2日経過するまで | ||
| 結核 | 病状に応じて、医師が感染の恐れがないと判断するまで | ||
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状に応じて、医師が感染の恐れがないと判断するまで | ||
| 新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日経過し、かつ、症状が経過してから1日を経過するまで | ||
| 第三種感染症 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 | 病状から医師において感染の恐れがないと認められるまで | |
| その他の感染症 (条件によって、出席停止措置が必要と考えられる疾患) | |||
| 溶連菌感染症、ウイルス性肝炎(A型・B型)、手足口病、伝染線紅斑(りんご病)、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎など | 全身状態が悪いなど、医師の判断によって出席停止を要する場合 | ||